「わたしたちについて」
~半径20キロ圏内から実現する、真のノーマライゼーション社会へ~

「特定非営利活動法人はぁもにぃ」は千葉市緑区を拠点に、誰もが自分らしくありのままで生きられる社会の実現を目指し、2007年12月に設立したNPO法人です。
自閉症スペクトラムと知的障がい特性を持ち生まれてきた娘が小学生の時に、担任教諭の方からいただいた言葉です。
「生まれてくる命の中には、一定の確率で障がい特性を持つ子どもたちがいます。
彼らは誰も引き受けたがらなかったであろう障がいという困難な特性を
『ぼくが(わたしが)引き受けます』と名乗り出てきてくれた存在なのだと思います。
優しい子どもたちだと思いませんか。
素晴らしい子どもたちだと思いませんか。
だから私は心の底から彼らのことを尊敬しているんです。」
その言葉を聞いた瞬間、わたしの中で我が子が障がいという困難な特性をもって生まれてきた意味が大きく変わっていきました。
優しくて素晴らしい彼らと共に、違いを知り、認め合い、支え合い、補い合いながら、誰もが自然な笑顔で過ごせるコミュニティを、彼らが生まれ育った地域の中に創りたいと強く願いました。
その願いを原点として、「働きたい」と願う誰もが「働ける」社会=「はぁもにぃソーシャルファームプロジェクト」に取り組んでいます。
わたしたちが目指す「ソーシャルファーム」は、「半径20キロ圏内から真のノーマライゼーション社会」を実現するための、実践的かつ持続可能な仕組みです。
地域に根ざした経済活動の中で、多様な人たちが「共に働く」ことを通じて、「共通の責任を担い、共に成長していけるコミュニティ」です。
そこでは、働く人それぞれが「できること」で役割を持ち、「できないこと」は仕組みやチームワークで補い合います。
そして、その活動の対価として得た報酬は、経済的な安定だけでなく、「必要とされている」という実感や、「誰かとつながっている」社会的承認をもたらします。
この「ソーシャルファーム」は、支援の対象として守られるだけの場でも、利益を目的とするだけの場でもありません。
地域の人々が互いの強みを活かし合い、寄り添いながら、「持続的に働ける場」=「新しい共助のモデル」です。
そしてその実現には、「ディーセント・ワーク(尊厳を守られ、やりがいを感じられる働き方)」が不可欠です。
「誰もが役割と責任を持ち、貢献しあえる職場環境」こそが、わたしたちが目指す「ソーシャルファーム」の基盤です。
持続可能な社会の一員として経済性・連携・共生を重視した「はぁもにぃソーシャルファーム」は、単に「働く場」をつくるのではなく、地域と経済をつなぎ、「必要とされる仕事」を生み出し続ける経済的持続性を追求しています。
地域の草刈り受託や農業・養蜂など、季節や環境に根ざした仕事を継続的に受注・運営することで、地域に根ざした収益構造を築いています。
また、地域の生産者・企業・行政・学校と協働し、役割分担と循環の仕組みを整えることで、ひとりの働き手の負担に依存しない「役割設計された協働チーム」として運営しています。
たとえば、養蜂部では「ミツバチとの共生」をテーマに掲げ、「チャレンジド(障がいや特性をもつ人)メンバーたち」が
「Bee Keeping(自然と共に蜂を養う)」という営みを通じて、地域の環境整備と経済活動をつなげています。
わたしたちは「Honey Hunting(はちみつを採る)」のではなく、「Bee Keeping(自然と共に蜂を養う)」という姿勢で活動し、みつばちたちが必要とするはちみつには手をつけず、みつばちたちが必要とする分を除いた剰余分のみを、一切手を加えることなくいただきそのはちみつ(完熟生)をびん詰めしています。
この「Bee Keeping(自然と共に蜂を養う)」事業から生まれた製品は、「チャレンジドフェアトレード(障がいや特性をもつ人たちによる誇りある仕事の成果を公正に評価・流通させる仕組み)商品」として販売されており、働く人々の誇りと経済的自立を支えています。
「みつばちとチャレンジドをまんなかに据えたこの仕組み」が、人と自然が調和して生きられる持続可能な地域社会づくりの、新しいモデルとなっていくことを願っています。
by特定非営利活動法人はぁもにぃ
※Challenged(チャレンジド)=挑戦という使命や課題、チャンスや資格を与えられた人→障がい者
※ノーマライゼーション=障がい者(社会的マイノリティ含む)が、一般市民と同様の社会生活をおくることを可能にする
ための環境整備を目指す理念
■Bee×ChallengedFairTrade

わたしたちは自然の営みと共生を学び、次世代につながる「環境保全型養蜂」を目指します。
養蜂とは「HoneyHunting(はちみつを採ること)」
ではなく、「BeeKeeping(自然と共に蜂を養うこと)」。
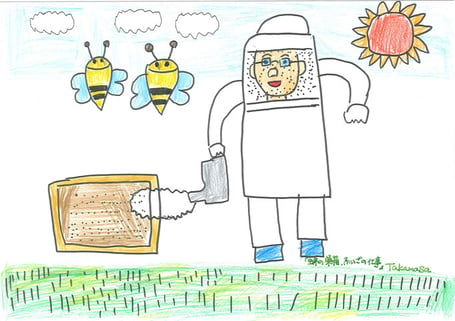
僕たち(わたしたち)は知的障がい・発達障がい特性を持ち生まれてきました。
僕たち(わたしたち)の特性や適性と養蜂の仕事はとても相性がよく、ひとりひとりが重要な役割を担い働いています。
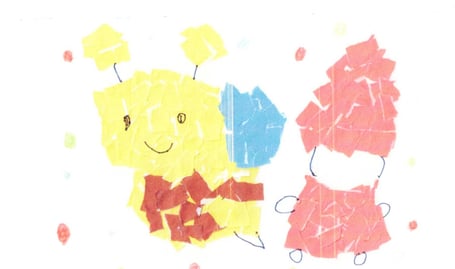
「みつばちたちを養い、地域の自然環境を整え、その報酬としてはちみつをいただき、はちみつを皆様にお届けすることで経済的自立が可能な報酬を得る」ことができます。
「ディーセント・ワーク(尊厳を守られ、やりがいを感じられる働き方)」はまさしくここにあると感じます。
ミツバチとともに生きる地域づくりは、人にも地球にもやさしい地域づくりです。
みつばちとチャレンジドをまんなかに、同じではなく違いを知り、違いに配慮しあい、誰にとっても何にとっても生きやすい、過ごしやすい環境をわたしたちが生まれ育った地域の中に整えていきます。
※FairTrade(フェアトレード)=公平で公正な取引の仕組み
■ありのままに自己肯定が可能な環境であること
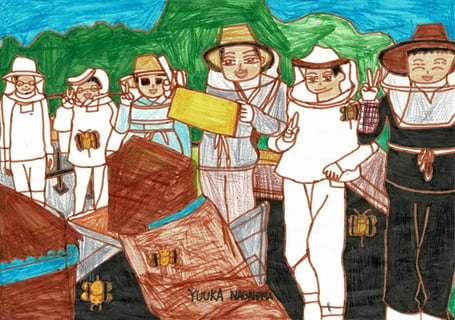
障がいの有無に関係なく、成長過程において自己肯定感を持って育つことは本当に大事ですが、違いや間違いを指摘され、注意されたり、叱責される経験をすることの多い、知的や発達障がい特性を持つ彼らにとって、これを持ち続けることは本当に難しいです。
それが出来ず、2次障がいで重いうつや統合失調症で苦しむ
成人当事者の方たちを本当に多く知るにつけ、そのことの大事さを痛感します。

知的や発達障がい特性を持つ人達は、実はとても自分の気持ちに正直で、自分の欲求や要求に素直です。
自分たちが肯定された空間では、周りを気にすることなく、本当にしたいこと、やりたいこと、好きなこと楽しいことに夢中になって取り組みます。迷いのないその姿に、楽しそうなその姿に、こちらのほうが憧れてしまいます。
これがいけないはずはないですよね?
というより、障がいの有無にかかわらず、みんながこのスタンスを持てれば、きっとみんなが生きやすくなり、もっと生活を人生を楽しめるんじゃないかと思うほどです。
変わらなければいけないのは、こちら側のほう・・・
でもそれも自分が変化・成長するというより、
「そのままでいい、ありのままでいい」と思えるようになるということ。
誰もが自分を肯定し、そう思うことができたら、それぞれがそれぞれでOK!ときっと思えるようになり、それぞれがしたいこと、できることに取り組めるようになっていくのではないでしょうか。
■自閉症とは
自閉症は目に見えない。誰も自閉症を見ることはできない。
それが私を私たらしめる事の1つである。
自閉症は私の脳の働き方に影響する。
脳はいつもスイッチが入っているコンピューターのようなもので、生命と学習活動を維持している。
自閉症のために脳の働き方が他の人と違うことがある。
自閉症の脳を持つことは自閉症オペレーティングシステムで動いているようなものである。
ほとんどの人は普通のオペレーティングシステムで動いている。
自閉症のために私は世界を特定の方法で経験する。
時にそれは他の人と同じだが、時に違ったものになる。
自閉症であることは間違っていることではない。
自閉症とはもうひとつの思考方法であり存在のありかたである。
引用:自閉症とは リー・マーカス(元チャペルヒルTEACCHセンター所長)